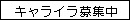14スレ目の74(ななよん)の妄想集@ウィキ
#01
最終更新:
14sure74
-
view
「またか・・・っ!」
そう言って、私は舌打ちをした。
漂っているという言葉が似合うような、不愉快な感覚が私の全身を支配していた。
「ちっ! この、音が・・・っ!」
小さな金属が回転して擦れ合うような甲高い音が、頭の中に響く。
脳内を掻き回されているような、頭痛と吐き気を伴う不快感に襲われ、私は耳を塞ごうとする。
しかし、身体は依然としてあの不愉快な浮遊感に支配されていて、動く気配を見せなかった。
私にそもそも身体と呼べる物があったのかさえ疑わしくなるほどに、動かなかった。
「くそ・・・っ! くそ・・・っ! くそぉ・・・っ!」
私は全ての不快感を吐き棄てるように悪態をついた。
現状、唯一私が自由に出来るのは意識だけだったからだ。
「くそ・・・っ! どうして・・・っ! いつも・・・っ!」
自分の身体が全く思い通りにならない、それが何故か悔しくて堪らなかった。
「――っ!!」
唐突に視界が開けた。
「また・・・かっ!」
開けた視界に広がっていたのは、沢山の『人間』という生き物が居て『家』という木造の物体が立ち並ぶ、『町』という光景だった。
「っ!?」
その光景に私の意識が一瞬だけ集中した隙に、『人間』の一人が視界に大きく映し出される。
「しま・・・っ!!」
私が全てを言い切るよりも先に、あの嫌な高音が響き出した。
「やめっ・・・うぁぁ・・・っ!!」
その直後、私の意識の中に、目の前に広がる光景とは別の光景が広がり出す。
そこでは、目の前の『人間』が映し出されていた。
「ぅぐっ・・・や・・・やめ・・・ろっ!」
激しい頭痛と吐き気に見舞われながら、私は叫ぶ。
しかし、今まで唯一に出来ていたはずの意識は、まるで言う事を聞かなかった。
途轍もない喪失感に打ちひしがれながらも、私は叫び続ける。
「やめ・・・ろっ・・・! やめ・・・ろぉ・・・っ! みせ・・・るな・・・っ!」
叫び続けている間も、私の意識は『人間』を映し続けていた。
意識に映っている『人間』は、視界に映った『人間』と同じ服装、同じ顔つき、同じ体付きをしていた。
違うのは、意識の中に映っている『人間』は、切り立った崖を歩いているという所だけだった。
「やめろ・・・もう・・・映す・・・な・・・っ!」
私は必死に叫び続けた。
このままでは、更なる不快感に見舞われると直感していたからだった。
しかし、意識はずっと『人間』を映し続ける。
「やめ・・・ろっ・・・や・・・めろぉっ! ・・・行く・・・なっ・・・! やめ・・・ろっ・・・もう・・・行く・・・なっ!」
気付けば私は、意識の中の『人間』に叫びかけていた。
更なる不快感に見舞われると直感した直後、何故か崖を行く『人間』が気になって仕方なくなったからだった。
私の叫びなど、聞えるはずがないだろう。
それでも何故か私は叫びかけずには居られなかった。
「やめ・・・っ! その・・・先はっ・・・!」
意識の中の映像が滲み出していく。
視界も滲み出していく。
「イヤ・・・・だ・・・っ! 行く・・・なぁぁっ!!」
意識の中に映る『人間』に声が届かない。
それが無性に悔しくて、悲しくて。
私が今込められる全てを賭けて叫んだ時だった。
「――っっ!!?」
意識の中の『人間』が、消えた。
岩が剥がれ落ちるような乾いた音と共に消えた。
直後、私が私足りうる全てを抉り取られたような喪失感に見舞われた。
「っぅああああああああああああああああああぁぁぁっっ!!」
喪失感に耐え切れず、私は叫んだ。
大型巨獣の雄叫びかと自らも錯覚するほどに、大きな声で叫んだ。
「――ぅぶっ!?」
不快感が目が回るような吐き気となって私を襲った。
「げほっ! がっ! う゛ぇっ! う゛ぇぇぇっ!」
吐き気に身を任せるように、私は吐いた。
なにを吐いたのかは、何故かよく分からなかったが、酷く悲しく、悔しく、やるせない感じがした。
「・・・何故・・・だ・・・っ!」
激しく澱み、ぐらついた意識と視界の中、私は呟くように問い掛けた。
「何故・・・こんな・・・物を・・・見せるっ!」
この感覚の、最後に決まって姿を現す『人間』に向かって私は問い掛けた。
「何故・・・私に・・・っ! 私に・・・どうしろと・・・っ! 私を・・・どうしたい・・・っ!」
その『人間』が、何故決まって最後に姿を現すのかは分からない。
そもそも、この事態がその『人間』の仕業である確証もない。
だがしかし、私にはその『人間』の仕業である気がしてならなかった。
「お前さえ・・・居なければっ! 私は・・・こんな・・・こんなっ!」
決まって最後に姿を現す『人間』は、やはり今回も姿を現した。
そして、やはり今回もただ黙って見ているだけで、答えようとしなかった。
私はそれが何故か悔しく、憎たらしく、悲しく感じていた。
「答えろっ! お前は・・・お前は・・・お前はぁっ!」
少しずつ姿を消していくその『人間』に、私は叫ぶ。
その『人間』の名前を、私は叫ぶ。
「――答えろっ!!」
その『人間』の名前は・・・。
~~~~
「――――っっ!!」
叫ぶと同時に、視界が暗転して不愉快な感覚が身体から消えていく。
変わりに熱っぽく重たい感覚が私を襲う。
私はその感覚が自らの身体から発せられている物であることを悟り、試しに右手に力を込めてみた。
すると私の右手がゆっくりと、握り締められていく感覚を感じることができた。
小さく安堵の溜め息をつきながら、私は作った右拳で額を軽く拭う。 じっとりとした不快な汗が拭った甲に広がったのを感じ、私は軽く舌打ちをした。
それから、私は意識の中に僅かに残っているあの不快感を払拭すべく、直前の自分の行動を思い出すことにした。
(・・・この横穴で眠りについた。 ・・・だな。)
私は、眠りについてからどれぐらいの時が経ったかを推測してみることにした。
(・・・1時間と言った所か。)
休息というには流石に短すぎるだろう。
しかし、元々長くこの場にいるつもりもなかった私は、この場を発つことにした。
(眠りにつく気にもなれないしな・・・。)
ゆっくりと立ち上がると、汗で濡れていたのか服がべったりと身体に張り付いてきた。
(ええいっ、鬱陶しいっ。)
まとわりつくようなおぞましさと肌寒さに悪態をつきながら、軽く柔軟体操をして身体をほぐす。
それから素早く身支度を整えて、私は歩き出した。
そして外へ出た瞬間、サングラスの隙間からわずかに差し込む光が、いつもより強く感じられた。
「・・・満月、だったな。」
満月の日は普段よりも周囲が明るく照らされるため、この星に生きる物、とりわけ『人間』の多くは満月の光を有難がった。
視界が少しでも利いた方が、事前に危険を察知しやすいことがその理由だ。
だがしかし、本当の所は違う。
この星に『人間』の多くは、色彩のある光景に異常とも思えるほど固執していた。
そんな物達にとって、色彩の元とも言える灯りのない状況はとても耐えられる物ではないのだ。
(・・・くだらんな。 灯りのある状況など、厄介なだけだ。)
私は大きく溜め息をつく。
私にとって満月の光は在り難い所か、はた迷惑な物でしかなかった。
視界が利きやすくなろうが、私には関係がない。
なぜなら、私の視界は常に瞼の裏にある光景を映しているからだ。
記憶している限り、私の視界は殆ど黒一色の、色彩のない光景が広がっていた。
たまに色彩のある光景が映る時は、決まってあの激しい頭痛と吐き気に見舞われていた。
(誰かに見つかると面倒だ、さっさと・・・!?)
出発しようと思った時だった。
私は遠くの方に『荷馬車』が地を駆ける音を聞いた気がした。
私は咄嗟にしゃがみ込み、地面に耳を近づける。
すると風の音に混じり3、4台の『荷馬車』が、此方へ近づいてくる音が聞き取れた。
どうやら、かなりの速さで移動しているようで、このままではすぐにでも接触することになるだろう。
(くっ! 迂闊だった!)
今私が居る場所は、絶壁が両脇を塞ぐ長い渓谷の中腹だ。
しかも、この場所は南北に真直ぐ伸びた、光の差し込みやすい長い直線であり、身を隠せるような場所は殆ど存在しない。
従って、このままでは必ず発見されてしまうだろう。
(ちぃっ・・・! せめて、満月でなければっ!)
視界の利かない普段の夜ならば、急いで横穴へ飛び込み入口を塞いでやり過ごすこともできただろう。
しかし、満月の光で明るく照らされている今では、万が一という可能性がある。
もしそんなことになれば、自ら墓穴を掘ってしまいかねない。
(私としたことが、無警戒に飛び出してしまったばかりにっ! くそっ! これも全て、あのっ!)
横穴を出る時に警戒を怠った自身が悪いことは百も承知だが、私はあの現象のせいにしたくて仕方がなかった。
悪態を付いた後、私は気持ちを切り替えるため大きな溜め息をついた。
(やり過ごせないのなら、見極めなくては。)
もう間もなく接触するであろう『荷馬車』の集団に向けて、私は全ての注意を集中させる。
アレらが私に害なすことができるかどうか、それを見極めるためだ。
もし、私にとって障害となりえるものならば先手を打っておきたい。
さっさとケリをつけるに越したことはないし、長引けば面倒なことになるからだ。
(・・・来るっ。)
車輪が回る音の高まりからそう推測し、私は身構える。
その直後、2台分の『荷馬車』の音が私の両脇を横切り、背後で地面を削る音を出す。
次いで、1台分の『荷馬車』が私の前で同じように地面を削る音を出した。
(止まったか。 ・・・停車音から考えると荷台は小さいが、中身は入ってそうだな。)
かなりの速度を出していた所から見ると、荷台の中にはなにか重要な物が入っているのかもしれない。
いくら満月の夜とはいえ、普通はあれほどの速度で走ることはない。
もし、予想通りに重要な物が入っているとして、そんな物を運んでいるにも関わらず止まったということは・・・。
(ちっ・・・。 コイツら、人目に触れると厄介な代物を運んでいたのか。)
単なる貴重品ならば、目的地まで急ぐ方が優先されるはずだから、私など構わずに走り抜けるか、止まるとしても直前で止まるはずだ。
それなのに、この集団は私を取り囲むように止まった。
輸送の現場を目撃した者を始末しなくては、後々面倒なことになりかねないと判断したに違いない。
停車してすぐに松明に灯を燈す音が全方位から聞こえてきたことも併せると、まず間違いないだろう。
(数は、12人か。 ・・・面倒だ、まとめて叩き斬ってしまえ。)
人目に触れられたくない物など、まとめて始末してしまっても問題はないし、もし問題があったとしても私には関係のないことだ。
それになにより、アイツらの視線が何故か私の胸元や下腹部に集中していて、全身をなめずり回されているような感じがして気持ちが悪い。
私は一応の警戒をしつつ、武器に手を伸ばした。
その時――。
そう言って、私は舌打ちをした。
漂っているという言葉が似合うような、不愉快な感覚が私の全身を支配していた。
「ちっ! この、音が・・・っ!」
小さな金属が回転して擦れ合うような甲高い音が、頭の中に響く。
脳内を掻き回されているような、頭痛と吐き気を伴う不快感に襲われ、私は耳を塞ごうとする。
しかし、身体は依然としてあの不愉快な浮遊感に支配されていて、動く気配を見せなかった。
私にそもそも身体と呼べる物があったのかさえ疑わしくなるほどに、動かなかった。
「くそ・・・っ! くそ・・・っ! くそぉ・・・っ!」
私は全ての不快感を吐き棄てるように悪態をついた。
現状、唯一私が自由に出来るのは意識だけだったからだ。
「くそ・・・っ! どうして・・・っ! いつも・・・っ!」
自分の身体が全く思い通りにならない、それが何故か悔しくて堪らなかった。
「――っ!!」
唐突に視界が開けた。
「また・・・かっ!」
開けた視界に広がっていたのは、沢山の『人間』という生き物が居て『家』という木造の物体が立ち並ぶ、『町』という光景だった。
「っ!?」
その光景に私の意識が一瞬だけ集中した隙に、『人間』の一人が視界に大きく映し出される。
「しま・・・っ!!」
私が全てを言い切るよりも先に、あの嫌な高音が響き出した。
「やめっ・・・うぁぁ・・・っ!!」
その直後、私の意識の中に、目の前に広がる光景とは別の光景が広がり出す。
そこでは、目の前の『人間』が映し出されていた。
「ぅぐっ・・・や・・・やめ・・・ろっ!」
激しい頭痛と吐き気に見舞われながら、私は叫ぶ。
しかし、今まで唯一に出来ていたはずの意識は、まるで言う事を聞かなかった。
途轍もない喪失感に打ちひしがれながらも、私は叫び続ける。
「やめ・・・ろっ・・・! やめ・・・ろぉ・・・っ! みせ・・・るな・・・っ!」
叫び続けている間も、私の意識は『人間』を映し続けていた。
意識に映っている『人間』は、視界に映った『人間』と同じ服装、同じ顔つき、同じ体付きをしていた。
違うのは、意識の中に映っている『人間』は、切り立った崖を歩いているという所だけだった。
「やめろ・・・もう・・・映す・・・な・・・っ!」
私は必死に叫び続けた。
このままでは、更なる不快感に見舞われると直感していたからだった。
しかし、意識はずっと『人間』を映し続ける。
「やめ・・・ろっ・・・や・・・めろぉっ! ・・・行く・・・なっ・・・! やめ・・・ろっ・・・もう・・・行く・・・なっ!」
気付けば私は、意識の中の『人間』に叫びかけていた。
更なる不快感に見舞われると直感した直後、何故か崖を行く『人間』が気になって仕方なくなったからだった。
私の叫びなど、聞えるはずがないだろう。
それでも何故か私は叫びかけずには居られなかった。
「やめ・・・っ! その・・・先はっ・・・!」
意識の中の映像が滲み出していく。
視界も滲み出していく。
「イヤ・・・・だ・・・っ! 行く・・・なぁぁっ!!」
意識の中に映る『人間』に声が届かない。
それが無性に悔しくて、悲しくて。
私が今込められる全てを賭けて叫んだ時だった。
「――っっ!!?」
意識の中の『人間』が、消えた。
岩が剥がれ落ちるような乾いた音と共に消えた。
直後、私が私足りうる全てを抉り取られたような喪失感に見舞われた。
「っぅああああああああああああああああああぁぁぁっっ!!」
喪失感に耐え切れず、私は叫んだ。
大型巨獣の雄叫びかと自らも錯覚するほどに、大きな声で叫んだ。
「――ぅぶっ!?」
不快感が目が回るような吐き気となって私を襲った。
「げほっ! がっ! う゛ぇっ! う゛ぇぇぇっ!」
吐き気に身を任せるように、私は吐いた。
なにを吐いたのかは、何故かよく分からなかったが、酷く悲しく、悔しく、やるせない感じがした。
「・・・何故・・・だ・・・っ!」
激しく澱み、ぐらついた意識と視界の中、私は呟くように問い掛けた。
「何故・・・こんな・・・物を・・・見せるっ!」
この感覚の、最後に決まって姿を現す『人間』に向かって私は問い掛けた。
「何故・・・私に・・・っ! 私に・・・どうしろと・・・っ! 私を・・・どうしたい・・・っ!」
その『人間』が、何故決まって最後に姿を現すのかは分からない。
そもそも、この事態がその『人間』の仕業である確証もない。
だがしかし、私にはその『人間』の仕業である気がしてならなかった。
「お前さえ・・・居なければっ! 私は・・・こんな・・・こんなっ!」
決まって最後に姿を現す『人間』は、やはり今回も姿を現した。
そして、やはり今回もただ黙って見ているだけで、答えようとしなかった。
私はそれが何故か悔しく、憎たらしく、悲しく感じていた。
「答えろっ! お前は・・・お前は・・・お前はぁっ!」
少しずつ姿を消していくその『人間』に、私は叫ぶ。
その『人間』の名前を、私は叫ぶ。
「――答えろっ!!」
その『人間』の名前は・・・。
~~~~
「――――っっ!!」
叫ぶと同時に、視界が暗転して不愉快な感覚が身体から消えていく。
変わりに熱っぽく重たい感覚が私を襲う。
私はその感覚が自らの身体から発せられている物であることを悟り、試しに右手に力を込めてみた。
すると私の右手がゆっくりと、握り締められていく感覚を感じることができた。
小さく安堵の溜め息をつきながら、私は作った右拳で額を軽く拭う。 じっとりとした不快な汗が拭った甲に広がったのを感じ、私は軽く舌打ちをした。
それから、私は意識の中に僅かに残っているあの不快感を払拭すべく、直前の自分の行動を思い出すことにした。
(・・・この横穴で眠りについた。 ・・・だな。)
私は、眠りについてからどれぐらいの時が経ったかを推測してみることにした。
(・・・1時間と言った所か。)
休息というには流石に短すぎるだろう。
しかし、元々長くこの場にいるつもりもなかった私は、この場を発つことにした。
(眠りにつく気にもなれないしな・・・。)
ゆっくりと立ち上がると、汗で濡れていたのか服がべったりと身体に張り付いてきた。
(ええいっ、鬱陶しいっ。)
まとわりつくようなおぞましさと肌寒さに悪態をつきながら、軽く柔軟体操をして身体をほぐす。
それから素早く身支度を整えて、私は歩き出した。
そして外へ出た瞬間、サングラスの隙間からわずかに差し込む光が、いつもより強く感じられた。
「・・・満月、だったな。」
満月の日は普段よりも周囲が明るく照らされるため、この星に生きる物、とりわけ『人間』の多くは満月の光を有難がった。
視界が少しでも利いた方が、事前に危険を察知しやすいことがその理由だ。
だがしかし、本当の所は違う。
この星に『人間』の多くは、色彩のある光景に異常とも思えるほど固執していた。
そんな物達にとって、色彩の元とも言える灯りのない状況はとても耐えられる物ではないのだ。
(・・・くだらんな。 灯りのある状況など、厄介なだけだ。)
私は大きく溜め息をつく。
私にとって満月の光は在り難い所か、はた迷惑な物でしかなかった。
視界が利きやすくなろうが、私には関係がない。
なぜなら、私の視界は常に瞼の裏にある光景を映しているからだ。
記憶している限り、私の視界は殆ど黒一色の、色彩のない光景が広がっていた。
たまに色彩のある光景が映る時は、決まってあの激しい頭痛と吐き気に見舞われていた。
(誰かに見つかると面倒だ、さっさと・・・!?)
出発しようと思った時だった。
私は遠くの方に『荷馬車』が地を駆ける音を聞いた気がした。
私は咄嗟にしゃがみ込み、地面に耳を近づける。
すると風の音に混じり3、4台の『荷馬車』が、此方へ近づいてくる音が聞き取れた。
どうやら、かなりの速さで移動しているようで、このままではすぐにでも接触することになるだろう。
(くっ! 迂闊だった!)
今私が居る場所は、絶壁が両脇を塞ぐ長い渓谷の中腹だ。
しかも、この場所は南北に真直ぐ伸びた、光の差し込みやすい長い直線であり、身を隠せるような場所は殆ど存在しない。
従って、このままでは必ず発見されてしまうだろう。
(ちぃっ・・・! せめて、満月でなければっ!)
視界の利かない普段の夜ならば、急いで横穴へ飛び込み入口を塞いでやり過ごすこともできただろう。
しかし、満月の光で明るく照らされている今では、万が一という可能性がある。
もしそんなことになれば、自ら墓穴を掘ってしまいかねない。
(私としたことが、無警戒に飛び出してしまったばかりにっ! くそっ! これも全て、あのっ!)
横穴を出る時に警戒を怠った自身が悪いことは百も承知だが、私はあの現象のせいにしたくて仕方がなかった。
悪態を付いた後、私は気持ちを切り替えるため大きな溜め息をついた。
(やり過ごせないのなら、見極めなくては。)
もう間もなく接触するであろう『荷馬車』の集団に向けて、私は全ての注意を集中させる。
アレらが私に害なすことができるかどうか、それを見極めるためだ。
もし、私にとって障害となりえるものならば先手を打っておきたい。
さっさとケリをつけるに越したことはないし、長引けば面倒なことになるからだ。
(・・・来るっ。)
車輪が回る音の高まりからそう推測し、私は身構える。
その直後、2台分の『荷馬車』の音が私の両脇を横切り、背後で地面を削る音を出す。
次いで、1台分の『荷馬車』が私の前で同じように地面を削る音を出した。
(止まったか。 ・・・停車音から考えると荷台は小さいが、中身は入ってそうだな。)
かなりの速度を出していた所から見ると、荷台の中にはなにか重要な物が入っているのかもしれない。
いくら満月の夜とはいえ、普通はあれほどの速度で走ることはない。
もし、予想通りに重要な物が入っているとして、そんな物を運んでいるにも関わらず止まったということは・・・。
(ちっ・・・。 コイツら、人目に触れると厄介な代物を運んでいたのか。)
単なる貴重品ならば、目的地まで急ぐ方が優先されるはずだから、私など構わずに走り抜けるか、止まるとしても直前で止まるはずだ。
それなのに、この集団は私を取り囲むように止まった。
輸送の現場を目撃した者を始末しなくては、後々面倒なことになりかねないと判断したに違いない。
停車してすぐに松明に灯を燈す音が全方位から聞こえてきたことも併せると、まず間違いないだろう。
(数は、12人か。 ・・・面倒だ、まとめて叩き斬ってしまえ。)
人目に触れられたくない物など、まとめて始末してしまっても問題はないし、もし問題があったとしても私には関係のないことだ。
それになにより、アイツらの視線が何故か私の胸元や下腹部に集中していて、全身をなめずり回されているような感じがして気持ちが悪い。
私は一応の警戒をしつつ、武器に手を伸ばした。
その時――。