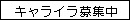14スレ目の74(ななよん)の妄想集@ウィキ
パートC
最終更新:
14sure74
-
view
「・・・なんだって!?剣術を教えろって!?」
「うん!私、一緒について行きたい!だから剣術を・・・」
「・・・ダメだ。」
確かにいくら素質があるとはいえ、素人同然の者を一緒に連れてはいけないだろう。
私もそれぐらいは予想していたので、彼が断ったことに関してはあまり驚かなかった。
「どうして?私が素人だから?戦力にならないから?」
「ちげぇよ。誰だって初めは素人だ。アンタは筋がいいから、鍛えればその辺のファイターよりもずっと頼りになる戦力だ。」
「じゃあなんで?私が、女だから?」
「それも違う。女でも立派に戦士として戦っているヤツを俺は何人も見ている。」
私は何故か段々と腹立たしくなってきて、気付けば声を張り上げていた。
「・・・じゃあなんでよ!私、少しでも力になりたいのに!私が居ると邪魔になるの!?」
「・・・分かった。連れてってやるよ。」
「えっ!?」
「ただし!」
彼は突然机の上においてあったナイフを取り私の手に握らせる。
そして、あろうことか自分の喉元へと無理矢理引き寄せた。
「お前が人を殺せればだ!さぁ!俺を殺して見せろ!」
「な・・・何を言ってるの?!」
この時の私には、彼がなんでこんなことをしたのか全く理解できなかった。
ただ、理不尽な理由で拒絶されたようにしか思えなかった。
「なんで!?こんなの・・・酷いよ!!」
「酷くねぇよ!俺は一人前の戦士以外とは組まねぇ!一人前の戦士ってのはな、人を殺せるヤツのことだ!」
引き戻そうとした私の手を彼は強引に引き戻して答えた。
「そんなっ!!でも、さっき私は鍛えれば強くなるって!!」
「ああ、言ったさ!でもな!いくら強くても人を殺せねぇヤツは使えねぇ!」
私の手を握る彼の手に力が入り、少しだけナイフが喉元に突き刺さる。
「いざという時、必ず躊躇う!躊躇えばソイツだけじゃなく、周りに居たヤツ全員が死ぬことだってあんだよ!」
「だ、だからって!どうして、私が・・・」
「その、いざと言う時ってのは、知り合いが敵になった時を言うんだ!」
彼の蒼い眼が真っ直ぐ私を捉えた。
その眼はすっかり忘れていたあの昏い激動を呼び覚ますような鋭く冷たい感じだった。
しかし、私も引き下がるつもりはなく、湧き上がる恐怖を必死に抑えつけながら叫んだ。
「じゃあ!もし私が敵になったら・・・」
「殺すさ!躊躇わずにな!そうしなければ、俺が殺される!俺が仕事をしてる世界はそういう世界だ!」
「う、ウソでしょ!?ねぇ!!」
「ウソじゃねぇよ!俺は・・・もう、何人も知り合いを殺してる!ソイツらの命を奪った咎を背負って生きている!」
私を見据える彼の眼はそれが嘘偽りでないことを物語っていた。
必要とあれば知り合いですら殺さねば生きていけない世界、それが彼の居る世界だった。
いったい、彼はそんな世界で何人の知り合いを殺して生き続けてきたのだろうか。
いったい、彼は幾つの咎を背負って生き続けてきたのだろうか。
私は胸が締め付けられるような思いに駆られた。
「でもな。俺、お前を殺した咎だけは背負いきる自信はねぇんだ。俺の一番大事な女の命奪ってまで、生きたくねぇんだよ・・・!」
「えっ?今・・・・・・。」
一番大事だとか、異性からそんなことを言われたのは多分この時が初めてだと思う。
「だからよ・・・お前だけには、俺と同じ世界に来て欲しくねぇんだ。これが、俺がお前を連れて行けない理由・・・。」
彼の声は今にも消えてしまいそうなぐらいに弱々しくて、私は彼がこのまま消えてしまうのではないかと不安になってしまった。
「そんな・・・そんなの・・・って・・・。」
「・・・なに、言ってんだろうな俺。あはは・・・すまんな。脅かしちまってさ。」
彼は私の手を優しく下ろして、ナイフを取り上げると再び机の上に置いた。
そして、ばつの悪そうな顔で頭を掻きながら軽く頭を下げた。
「まっ、兎に角アンタを危険な目に遭わせたくねぇし、今までみたいに此処で待っててくれた方が・・・」
「イヤ・・・。」
「えっ?」
私でも何故かはよく分からなかった。
しかし、此処で諦めてしまったら永遠に彼に近付けなくなる気がした。
「イヤって、アンタ・・・」
「分かってる!私は・・・一人前の戦士にはなれない!なりたくない!でも!それでも一緒に行きたい!」
「でも俺は・・・」
「私、もう待つのイヤ!傍に居たい!少しでも長く!1秒でも長く!」
私は涙が溢れるのも気にせず彼にしがみ付き叫んだ。
私には人を、彼を殺すことなんてできない。彼の言う一人前の戦士にはとてもなれない。
そう思っていた。それでも、私の心の奥底で彼と離れたくないという思いが止め処【とめど】なく湧き出していた。
彼は驚いた表情を見せるが、優しく抱きしめてくれた。
「・・・そっか、アンタ。俺みたいなヤツをそんなに大切に想ってくれてんだな・・・。」
「っ!」
この時、彼に言われて私は初めて知った。
人を大切に想うとはこういう気持ちになることなんだと。
「・・・ありがとな。嬉しいぜ。」
「わっ・・・。」
顔を上げた私の頭を彼が笑顔で優しく撫でてくれた。
少しだけ驚いたが、彼の暖かい掌が気持ちよくて私はゆっくり目を閉じた。
「・・・剣術、教えてやるよ。」
「・・・えっ!?・・・でもっ、私は・・・。」
「ああ、仕事には一緒に連れて行けないし、連れて行きたくはない。」
「そ、それじゃあ・・・。」
彼は私の両肩に手を乗せて優しく引き離すと、屈託のない笑顔を見せた。
「ふふっ、俺の修行は厳しいぞ~?途中で音を上げるなよ?ネス。」
「・・・は、はい!よろしくお願いします!師匠!」
私は深く頭を下げた。
嬉しさのあまりに涙が滲み、視界が少しだけ滲んでしまった。
「し、師匠・・・悪くねぇ響きだな♪よし、ネス。早速だが・・・。」
「ナニするの?師匠!」
私は期待に胸を高鳴らせて彼の言葉を待った。
彼は少しだけ考える素振りを見せてから真顔で口を開いた。
「・・・ハラ減った。何か喰おう。」
「ハァ~~~ッ!?」
待ちわびた言葉の続きが如何にも彼らしい一言で、私は開いた口が塞がらなかった。
私が唖然としている様子も気にせず彼はお腹をさすって空腹を誇示しながら言った。
「なにポカンとしてんだ?ハラが減ってちゃ修行はできねぇぞ?ほら、さっさと準備準備!」
「・・・はぁ~い。」
「返事はシャキっと!」
「はい!師匠!」
~~~~
私が仕事への同行を申し出たあの日から、5年ほど歳月が過ぎた。
彼の修行は想像を絶する厳しさで、生傷が絶えることはなかった。
それでも、私は幸せで充実した日々だと感じていた。
今私が立っている世界と、彼が立っている世界の間には絶望的に深く広い崖がある。
私が一人前の戦士にならない限り、いくら強くなってもその崖を越えることはできない。
私が一人前の戦士になって、その崖を越えてくることを彼は望んでいない。
つまり、結局の所こんなことをいくらしたって私は彼の傍には行けない。
それなのに彼が崖の向こうから、一本の糸を投げてくれたことが堪らなく嬉しかった。
一本の糸を通して、彼の輝き、彼の想いに触れられることが嬉しかった。
だから、私はどんなに苦しくても歯を食いしばりついていった。
「あっ、師匠。」
「んっ?もう喰い終わったのかネス。」
「違うよ、アレ・・・。」
私は窓の外に見えた獣を指差して問いかけた。
「ああ、もうそんな時期か。」
「そうだね・・・。」
体長は1メートル前後でたるんだ頬の肉と強面が特徴のその獣は、名前をサントドッグと言う。
見た目の割りに温厚で臆病、人里離れた森の中で1匹から数匹の群れで暮らしている獣だ。
サントドッグは年に1度だけ繁殖期を迎え、その性格が豹変する。
「気をつけないと喰われるぞ、特にネスは美味しそうだからなっ♪」
「うん、分かってる。気をつけるよ。」
「あーでも、過去に喰われたのはか弱い美女か子供だけだって話だからなぁ~・・・ネスはだいじょ・・・あだっ!」
「んもぉ!早く修行の続きしようヨ!師匠!!」
私は何故かとてもバカにされた気がしたので、彼の足を思い切り踏みつけ席を立ち彼の分の料理もさげてしまった。
慌てて彼が情けない声で謝りながら後を追ってくるので、私は内心してやったりとほくそえみながら不機嫌そうな顔で彼に料理を返した。
今にして思えば、この時何故見慣れたはずのあの獣の存在に気付いたのかもう少し深く考えるべきだった。
「・・・じゃ、行って来るぜ♪帰ってくるまで修行、サボるんじゃね~ぞ?」
「分かってるよ師匠、気をつけてネ。」
その数日後、彼は久しぶりの大仕事が入ったと喜び勇んで出かけていった。
初めて出会ったあの日に彼から手渡された私の唯一の持ち物、白い布を腰にベルト代わりに巻き付けて出て行く彼の姿を私は手を振って見送った。
彼が帰ってくる予定の日、私は近くの集落まで買出しに出かけていた。
その日は丁度、私が彼と出会った日だったからだ。
今まで祝ったことはなかったが、大仕事を終えて帰ってくる日と重なったので折角だからと思い立ったのが始まりだった。
祝宴の準備を終え、一際明るい夜空の下、家の前で彼の帰りを待っていた時だった。
あの男が私の目の前に現れた。
口元に今と変わらない憎たらしい笑みを浮かべて、あの男が現れた。
「・・・誰?」
「ほほぉ、女と暮らし始めたとは聞いていたが本当だったとはな・・・。」
「誰って聞いてるの!」
「おっと、これは失礼した。私はオルグ=G=ハント。此処には仕事で来ただけだよ、ネール=A=ファリス君。」
「どうして私の名前を!?」
「アサシンという人種はな、標的の身辺調査は完璧にするものだ。覚えておくといい、ネス君。」
あの男の襲来目的が彼であることを悟った私は、咄嗟に扉の傍に立てかけてあった木刀を取り上げて構えた。
あの男は全く動じる様子もなく余裕の表情で私を見ていた。
「ほほぉ、バカではないようだな。・・・だが、優秀というワケでもないな。」
「・・・どういうこと?」
「まず初めに、君の実力では正攻法で私を倒すことは不可能だ。精々足止めができる程度だろう。次に、そんな棒切れでは万が一でも私を倒せない。」
そう言ってあの男は私の足元に一本の剣を投げつけてきた。
驚いた私は飛び退いて様子を見るが、あの男が攻めてくる気配はなかった。
「なんのつもり?」
「なに、万が一で勝てるよう剣を貸してやろうというだけだ。邪魔者は誰であれ消すのが信条とはいえ、丸腰同然の者が相手では気が引けるしな。」
(気が引ける?・・・よく言うよ!)
「その剣を取れば君は少なくとも私の足止めができて、運がよければ勝てるかもしれないのだ。悪くない選択だと思うが?」
冷静に考えればこれは私を自分のペースに引きずり込むあの男の罠だと簡単に分かったはずだった。
しかし、この時の私はそこまで冷静になることはできなかった。
「そんなもの!」
「・・・疲れて帰ってくる師匠の役に立ちたいのだろう?師匠のために少しでも私を消耗させておきたいし、できれば師匠の手を煩わせず済ませたいのだろう?」
「――!?」
考えていることをずばり言い当てられ、私は平常心を失ってしまった。
私はあの男の口車に乗せられどんどん深みへと引きずりこまれて行った。
「さあ、剣を取ってついて来るのだ。私の死体を家の前に置いておきたくはあるまい?」
「・・・殊勝【しゅしょう】な心掛けネッ!!いいよ!望み通りにしてあげる!!」
私はあの男の投げた剣を拾い上げ、初めて持つ剣の重みに少しだけ戸惑いながらもあの男の後を追った。
あの男は家から伸びる林道を少し進んだ所で立ち止まると、私に斬りかかってきた。
突然の攻撃に慌てながらも私は何とか防ぎ、あの男との戦いの火蓋が切って落とされた。
「ほぉ~、思っていたよりも鍛えられてるではないか。」
「くっ!・・・このぉっ!!」
(この男、かなり強い!師匠が帰ってくるまで、少しでも消耗させないと!)
悔しいがあの男の言うとおり、この時の私の実力では足止めが限界だった。
私は既に息が上がっているのに、あの男は表情一つ変えず私を見てほくそえんでいた。
「身のこなしも技術も一級品だ。だが・・・」
「たぁぁぁーーっ!!」
「力不足だな、ネス君!」
「きゃあ!!」
あの男は私の剣を自らの剣で受け止めるとそのまま力任せに突き飛ばしてきた。
私は身体が一瞬だけ宙に浮き、それから尻餅をつく形で背中から着地した。
その隙を逃すまいとあの男が連続突きを放ってきた。
私は地面を転がるようにかわしながら勢いをつけ、地面を突き飛ばして飛び起きた。
「あの程度で吹き飛ぶとは重量不足もあるな。しかしまぁ、女性ならば仕方もあるまい。」
「私が・・・女だから・・・だって・・・?」
確かに私は女性だ。しかし、師匠は私を一人の戦士として鍛えてくれた。
そこには女性だからという妥協は一切なかった。
私の体格的に重量不足は100歩譲って認めても、力不足は決して女性だからというワケではない。
私は師匠の鍛え方を遠巻きに侮辱された気がして心底腹が立った。
「そんなの関係ない!私は女だからって加減されたことなんてないよ!」
「ほぉー・・・。では単純に師匠の力不足が、弟子の君に反映されたということだな?」
「くっ!!ああ言えばこう言うヤツ!私大嫌い!!」
私の不出来を師匠のせいといわれ、私は遂に堪忍袋の緒が切れた。
私は剣を力任せに振り回しあの男へ何度も叩き付けた。
あの男は私の剣を涼しい顔で払い続けて、私の神経を逆撫でしてきた。
「はぁぁぁーーっ!!」
「フフッ、大した足止めもできない利用価値無しの女を持って、彼もさぞ悲しいだろうな。」
「うるさい!黙れっ!黙れぇぇっっ!」
「だが・・・。」
今思えば、最初から私の姿はあの男の眼中になかったのだ。
ただ、私があの人を殺すのに利用価値があるから付き合ったまでのことだったのだ。
「私が彼の女として利用価値を見出してあげよう!ネール=A=ファリス君!!」
「―――しまっ?!」
あの男は私が力任せに振り下ろした剣を払い上げ、一歩前へ踏み込んだ。
私は払い上げられた剣に両手を取られ、次に来る一撃をどうすることもできなかった。
「ぐっあああああぁぁぁぁぁーーっ!!」
あの男の剣先が一筋の閃光となって、私の胸を横になぞった。
その刹那、今までのどんな修行でも味わったことのない痛みと苦しみが私の全身を駆け巡り、私は剣を棄てて蹲ってしまった。
どんなに身を丸めてもなぞられた後から血が溢れだし、私の意識を奪っていった。
「ネス!・・・許さねぇっ!!」
「ようやく師匠のお帰りか。私などに構ってていいのかね?早く手当てしないと君の女が死ぬぞ?」
「そうだな!そーいうワケだからお前はさっさと倒れろ!」
朦朧とした意識の中、遠くの方で師匠とあの男の声が聞こえた。
それがまるで彼の居る世界と私が居る世界の距離みたいな感じに思えて、私はこの時、身を持って彼の居る世界の遠さを知ることとなった。
「沢山予備の得物を持ってきたのは流石と言ってやるが、ちょっと足りなかったみたいだなっ!」
「ふっ。流石は噂のブレイカーだ。ヘタに受け止めると得物ごと斬られてしまうな。」
段々と薄れていく意識の中、師匠があの男を追い詰めていることに私は安心していた。
私が不出来なだけで、彼は十分強いということがもう少しで証明されるのだ。
あの男の憎たらしい笑みが恐怖と後悔で引き攣る【ひきつる】様が、もう少しで見れるのだ。
しかし、少しだけ冷静さを取り戻していた私はふとあの男の言葉が脳裏を過ぎった。
(『私が彼の女として利用価値を見出してあげよう』・・・って、どういうコト?)
これがあの男の言う利用価値だとしたら、何一つあの男に利益を齎して【もたらして】いない。
悪戯に彼を刺激して彼の士気を高めてしまっただけだ。
私にとっては彼の士気が上がることは良いことではある。そういう意味では利用価値はあったとも言える。
しかし、あの男が敵に塩を送るような真似をしないのはたった今、身を持って学習済みだ。
「・・・しかし、あれだけの出血だ。ヤツらは相当刺激されているだろうな。」
「ヤツら?・・・しまった!ネス!!」
(―――えっ?)
遠くで呟くようなあの男の声と殆ど同時に、私の目の前から地面を轟かす低い唸り声が聞こえだした。
そして姿を現したのはこの前窓の外に見つけた獣、サントドッグだった。
繁殖期を迎えたサントドッグは血の臭いを敏感に嗅ぎつけ、できる限り弱った獲物を狩ることで体力をつけようとする。
目の前のサントドッグは私の血の臭いに引き寄せられたのだ。
あの獣の世界では基本的に人間の女性は弱い動物と見られていて、しかも出血多量で満足に動けない今の私はあの獣にとって・・・。
(格好の、標的――!?)
「だぁぁーっ!・・・うぐっ!!」
「・・・えっ。」
私へ飛び掛ってきたサントドッグを彼が間に躍りこみ殴り飛ばした。
その次の瞬間、彼が呻き声を上げ硬直する。それから私の頭や背中にかかる温かい液体。
「う・・そ・・・し・・・ししょぉぉぉぉぉぉぉ!!」
私は残っていた力を振り絞って彼の名を叫んだ。
遠くであの男の嘲笑が聞こえ、そのまま何かを言い残して立ち去って行った。
後は放っておいても彼も私も死ぬと考えたのだろう。
実際、この時の私は漆黒の谷底に堕ちながらこのまま二人とも死んでしまうと思っていた。
「うん!私、一緒について行きたい!だから剣術を・・・」
「・・・ダメだ。」
確かにいくら素質があるとはいえ、素人同然の者を一緒に連れてはいけないだろう。
私もそれぐらいは予想していたので、彼が断ったことに関してはあまり驚かなかった。
「どうして?私が素人だから?戦力にならないから?」
「ちげぇよ。誰だって初めは素人だ。アンタは筋がいいから、鍛えればその辺のファイターよりもずっと頼りになる戦力だ。」
「じゃあなんで?私が、女だから?」
「それも違う。女でも立派に戦士として戦っているヤツを俺は何人も見ている。」
私は何故か段々と腹立たしくなってきて、気付けば声を張り上げていた。
「・・・じゃあなんでよ!私、少しでも力になりたいのに!私が居ると邪魔になるの!?」
「・・・分かった。連れてってやるよ。」
「えっ!?」
「ただし!」
彼は突然机の上においてあったナイフを取り私の手に握らせる。
そして、あろうことか自分の喉元へと無理矢理引き寄せた。
「お前が人を殺せればだ!さぁ!俺を殺して見せろ!」
「な・・・何を言ってるの?!」
この時の私には、彼がなんでこんなことをしたのか全く理解できなかった。
ただ、理不尽な理由で拒絶されたようにしか思えなかった。
「なんで!?こんなの・・・酷いよ!!」
「酷くねぇよ!俺は一人前の戦士以外とは組まねぇ!一人前の戦士ってのはな、人を殺せるヤツのことだ!」
引き戻そうとした私の手を彼は強引に引き戻して答えた。
「そんなっ!!でも、さっき私は鍛えれば強くなるって!!」
「ああ、言ったさ!でもな!いくら強くても人を殺せねぇヤツは使えねぇ!」
私の手を握る彼の手に力が入り、少しだけナイフが喉元に突き刺さる。
「いざという時、必ず躊躇う!躊躇えばソイツだけじゃなく、周りに居たヤツ全員が死ぬことだってあんだよ!」
「だ、だからって!どうして、私が・・・」
「その、いざと言う時ってのは、知り合いが敵になった時を言うんだ!」
彼の蒼い眼が真っ直ぐ私を捉えた。
その眼はすっかり忘れていたあの昏い激動を呼び覚ますような鋭く冷たい感じだった。
しかし、私も引き下がるつもりはなく、湧き上がる恐怖を必死に抑えつけながら叫んだ。
「じゃあ!もし私が敵になったら・・・」
「殺すさ!躊躇わずにな!そうしなければ、俺が殺される!俺が仕事をしてる世界はそういう世界だ!」
「う、ウソでしょ!?ねぇ!!」
「ウソじゃねぇよ!俺は・・・もう、何人も知り合いを殺してる!ソイツらの命を奪った咎を背負って生きている!」
私を見据える彼の眼はそれが嘘偽りでないことを物語っていた。
必要とあれば知り合いですら殺さねば生きていけない世界、それが彼の居る世界だった。
いったい、彼はそんな世界で何人の知り合いを殺して生き続けてきたのだろうか。
いったい、彼は幾つの咎を背負って生き続けてきたのだろうか。
私は胸が締め付けられるような思いに駆られた。
「でもな。俺、お前を殺した咎だけは背負いきる自信はねぇんだ。俺の一番大事な女の命奪ってまで、生きたくねぇんだよ・・・!」
「えっ?今・・・・・・。」
一番大事だとか、異性からそんなことを言われたのは多分この時が初めてだと思う。
「だからよ・・・お前だけには、俺と同じ世界に来て欲しくねぇんだ。これが、俺がお前を連れて行けない理由・・・。」
彼の声は今にも消えてしまいそうなぐらいに弱々しくて、私は彼がこのまま消えてしまうのではないかと不安になってしまった。
「そんな・・・そんなの・・・って・・・。」
「・・・なに、言ってんだろうな俺。あはは・・・すまんな。脅かしちまってさ。」
彼は私の手を優しく下ろして、ナイフを取り上げると再び机の上に置いた。
そして、ばつの悪そうな顔で頭を掻きながら軽く頭を下げた。
「まっ、兎に角アンタを危険な目に遭わせたくねぇし、今までみたいに此処で待っててくれた方が・・・」
「イヤ・・・。」
「えっ?」
私でも何故かはよく分からなかった。
しかし、此処で諦めてしまったら永遠に彼に近付けなくなる気がした。
「イヤって、アンタ・・・」
「分かってる!私は・・・一人前の戦士にはなれない!なりたくない!でも!それでも一緒に行きたい!」
「でも俺は・・・」
「私、もう待つのイヤ!傍に居たい!少しでも長く!1秒でも長く!」
私は涙が溢れるのも気にせず彼にしがみ付き叫んだ。
私には人を、彼を殺すことなんてできない。彼の言う一人前の戦士にはとてもなれない。
そう思っていた。それでも、私の心の奥底で彼と離れたくないという思いが止め処【とめど】なく湧き出していた。
彼は驚いた表情を見せるが、優しく抱きしめてくれた。
「・・・そっか、アンタ。俺みたいなヤツをそんなに大切に想ってくれてんだな・・・。」
「っ!」
この時、彼に言われて私は初めて知った。
人を大切に想うとはこういう気持ちになることなんだと。
「・・・ありがとな。嬉しいぜ。」
「わっ・・・。」
顔を上げた私の頭を彼が笑顔で優しく撫でてくれた。
少しだけ驚いたが、彼の暖かい掌が気持ちよくて私はゆっくり目を閉じた。
「・・・剣術、教えてやるよ。」
「・・・えっ!?・・・でもっ、私は・・・。」
「ああ、仕事には一緒に連れて行けないし、連れて行きたくはない。」
「そ、それじゃあ・・・。」
彼は私の両肩に手を乗せて優しく引き離すと、屈託のない笑顔を見せた。
「ふふっ、俺の修行は厳しいぞ~?途中で音を上げるなよ?ネス。」
「・・・は、はい!よろしくお願いします!師匠!」
私は深く頭を下げた。
嬉しさのあまりに涙が滲み、視界が少しだけ滲んでしまった。
「し、師匠・・・悪くねぇ響きだな♪よし、ネス。早速だが・・・。」
「ナニするの?師匠!」
私は期待に胸を高鳴らせて彼の言葉を待った。
彼は少しだけ考える素振りを見せてから真顔で口を開いた。
「・・・ハラ減った。何か喰おう。」
「ハァ~~~ッ!?」
待ちわびた言葉の続きが如何にも彼らしい一言で、私は開いた口が塞がらなかった。
私が唖然としている様子も気にせず彼はお腹をさすって空腹を誇示しながら言った。
「なにポカンとしてんだ?ハラが減ってちゃ修行はできねぇぞ?ほら、さっさと準備準備!」
「・・・はぁ~い。」
「返事はシャキっと!」
「はい!師匠!」
~~~~
私が仕事への同行を申し出たあの日から、5年ほど歳月が過ぎた。
彼の修行は想像を絶する厳しさで、生傷が絶えることはなかった。
それでも、私は幸せで充実した日々だと感じていた。
今私が立っている世界と、彼が立っている世界の間には絶望的に深く広い崖がある。
私が一人前の戦士にならない限り、いくら強くなってもその崖を越えることはできない。
私が一人前の戦士になって、その崖を越えてくることを彼は望んでいない。
つまり、結局の所こんなことをいくらしたって私は彼の傍には行けない。
それなのに彼が崖の向こうから、一本の糸を投げてくれたことが堪らなく嬉しかった。
一本の糸を通して、彼の輝き、彼の想いに触れられることが嬉しかった。
だから、私はどんなに苦しくても歯を食いしばりついていった。
「あっ、師匠。」
「んっ?もう喰い終わったのかネス。」
「違うよ、アレ・・・。」
私は窓の外に見えた獣を指差して問いかけた。
「ああ、もうそんな時期か。」
「そうだね・・・。」
体長は1メートル前後でたるんだ頬の肉と強面が特徴のその獣は、名前をサントドッグと言う。
見た目の割りに温厚で臆病、人里離れた森の中で1匹から数匹の群れで暮らしている獣だ。
サントドッグは年に1度だけ繁殖期を迎え、その性格が豹変する。
「気をつけないと喰われるぞ、特にネスは美味しそうだからなっ♪」
「うん、分かってる。気をつけるよ。」
「あーでも、過去に喰われたのはか弱い美女か子供だけだって話だからなぁ~・・・ネスはだいじょ・・・あだっ!」
「んもぉ!早く修行の続きしようヨ!師匠!!」
私は何故かとてもバカにされた気がしたので、彼の足を思い切り踏みつけ席を立ち彼の分の料理もさげてしまった。
慌てて彼が情けない声で謝りながら後を追ってくるので、私は内心してやったりとほくそえみながら不機嫌そうな顔で彼に料理を返した。
今にして思えば、この時何故見慣れたはずのあの獣の存在に気付いたのかもう少し深く考えるべきだった。
「・・・じゃ、行って来るぜ♪帰ってくるまで修行、サボるんじゃね~ぞ?」
「分かってるよ師匠、気をつけてネ。」
その数日後、彼は久しぶりの大仕事が入ったと喜び勇んで出かけていった。
初めて出会ったあの日に彼から手渡された私の唯一の持ち物、白い布を腰にベルト代わりに巻き付けて出て行く彼の姿を私は手を振って見送った。
彼が帰ってくる予定の日、私は近くの集落まで買出しに出かけていた。
その日は丁度、私が彼と出会った日だったからだ。
今まで祝ったことはなかったが、大仕事を終えて帰ってくる日と重なったので折角だからと思い立ったのが始まりだった。
祝宴の準備を終え、一際明るい夜空の下、家の前で彼の帰りを待っていた時だった。
あの男が私の目の前に現れた。
口元に今と変わらない憎たらしい笑みを浮かべて、あの男が現れた。
「・・・誰?」
「ほほぉ、女と暮らし始めたとは聞いていたが本当だったとはな・・・。」
「誰って聞いてるの!」
「おっと、これは失礼した。私はオルグ=G=ハント。此処には仕事で来ただけだよ、ネール=A=ファリス君。」
「どうして私の名前を!?」
「アサシンという人種はな、標的の身辺調査は完璧にするものだ。覚えておくといい、ネス君。」
あの男の襲来目的が彼であることを悟った私は、咄嗟に扉の傍に立てかけてあった木刀を取り上げて構えた。
あの男は全く動じる様子もなく余裕の表情で私を見ていた。
「ほほぉ、バカではないようだな。・・・だが、優秀というワケでもないな。」
「・・・どういうこと?」
「まず初めに、君の実力では正攻法で私を倒すことは不可能だ。精々足止めができる程度だろう。次に、そんな棒切れでは万が一でも私を倒せない。」
そう言ってあの男は私の足元に一本の剣を投げつけてきた。
驚いた私は飛び退いて様子を見るが、あの男が攻めてくる気配はなかった。
「なんのつもり?」
「なに、万が一で勝てるよう剣を貸してやろうというだけだ。邪魔者は誰であれ消すのが信条とはいえ、丸腰同然の者が相手では気が引けるしな。」
(気が引ける?・・・よく言うよ!)
「その剣を取れば君は少なくとも私の足止めができて、運がよければ勝てるかもしれないのだ。悪くない選択だと思うが?」
冷静に考えればこれは私を自分のペースに引きずり込むあの男の罠だと簡単に分かったはずだった。
しかし、この時の私はそこまで冷静になることはできなかった。
「そんなもの!」
「・・・疲れて帰ってくる師匠の役に立ちたいのだろう?師匠のために少しでも私を消耗させておきたいし、できれば師匠の手を煩わせず済ませたいのだろう?」
「――!?」
考えていることをずばり言い当てられ、私は平常心を失ってしまった。
私はあの男の口車に乗せられどんどん深みへと引きずりこまれて行った。
「さあ、剣を取ってついて来るのだ。私の死体を家の前に置いておきたくはあるまい?」
「・・・殊勝【しゅしょう】な心掛けネッ!!いいよ!望み通りにしてあげる!!」
私はあの男の投げた剣を拾い上げ、初めて持つ剣の重みに少しだけ戸惑いながらもあの男の後を追った。
あの男は家から伸びる林道を少し進んだ所で立ち止まると、私に斬りかかってきた。
突然の攻撃に慌てながらも私は何とか防ぎ、あの男との戦いの火蓋が切って落とされた。
「ほぉ~、思っていたよりも鍛えられてるではないか。」
「くっ!・・・このぉっ!!」
(この男、かなり強い!師匠が帰ってくるまで、少しでも消耗させないと!)
悔しいがあの男の言うとおり、この時の私の実力では足止めが限界だった。
私は既に息が上がっているのに、あの男は表情一つ変えず私を見てほくそえんでいた。
「身のこなしも技術も一級品だ。だが・・・」
「たぁぁぁーーっ!!」
「力不足だな、ネス君!」
「きゃあ!!」
あの男は私の剣を自らの剣で受け止めるとそのまま力任せに突き飛ばしてきた。
私は身体が一瞬だけ宙に浮き、それから尻餅をつく形で背中から着地した。
その隙を逃すまいとあの男が連続突きを放ってきた。
私は地面を転がるようにかわしながら勢いをつけ、地面を突き飛ばして飛び起きた。
「あの程度で吹き飛ぶとは重量不足もあるな。しかしまぁ、女性ならば仕方もあるまい。」
「私が・・・女だから・・・だって・・・?」
確かに私は女性だ。しかし、師匠は私を一人の戦士として鍛えてくれた。
そこには女性だからという妥協は一切なかった。
私の体格的に重量不足は100歩譲って認めても、力不足は決して女性だからというワケではない。
私は師匠の鍛え方を遠巻きに侮辱された気がして心底腹が立った。
「そんなの関係ない!私は女だからって加減されたことなんてないよ!」
「ほぉー・・・。では単純に師匠の力不足が、弟子の君に反映されたということだな?」
「くっ!!ああ言えばこう言うヤツ!私大嫌い!!」
私の不出来を師匠のせいといわれ、私は遂に堪忍袋の緒が切れた。
私は剣を力任せに振り回しあの男へ何度も叩き付けた。
あの男は私の剣を涼しい顔で払い続けて、私の神経を逆撫でしてきた。
「はぁぁぁーーっ!!」
「フフッ、大した足止めもできない利用価値無しの女を持って、彼もさぞ悲しいだろうな。」
「うるさい!黙れっ!黙れぇぇっっ!」
「だが・・・。」
今思えば、最初から私の姿はあの男の眼中になかったのだ。
ただ、私があの人を殺すのに利用価値があるから付き合ったまでのことだったのだ。
「私が彼の女として利用価値を見出してあげよう!ネール=A=ファリス君!!」
「―――しまっ?!」
あの男は私が力任せに振り下ろした剣を払い上げ、一歩前へ踏み込んだ。
私は払い上げられた剣に両手を取られ、次に来る一撃をどうすることもできなかった。
「ぐっあああああぁぁぁぁぁーーっ!!」
あの男の剣先が一筋の閃光となって、私の胸を横になぞった。
その刹那、今までのどんな修行でも味わったことのない痛みと苦しみが私の全身を駆け巡り、私は剣を棄てて蹲ってしまった。
どんなに身を丸めてもなぞられた後から血が溢れだし、私の意識を奪っていった。
「ネス!・・・許さねぇっ!!」
「ようやく師匠のお帰りか。私などに構ってていいのかね?早く手当てしないと君の女が死ぬぞ?」
「そうだな!そーいうワケだからお前はさっさと倒れろ!」
朦朧とした意識の中、遠くの方で師匠とあの男の声が聞こえた。
それがまるで彼の居る世界と私が居る世界の距離みたいな感じに思えて、私はこの時、身を持って彼の居る世界の遠さを知ることとなった。
「沢山予備の得物を持ってきたのは流石と言ってやるが、ちょっと足りなかったみたいだなっ!」
「ふっ。流石は噂のブレイカーだ。ヘタに受け止めると得物ごと斬られてしまうな。」
段々と薄れていく意識の中、師匠があの男を追い詰めていることに私は安心していた。
私が不出来なだけで、彼は十分強いということがもう少しで証明されるのだ。
あの男の憎たらしい笑みが恐怖と後悔で引き攣る【ひきつる】様が、もう少しで見れるのだ。
しかし、少しだけ冷静さを取り戻していた私はふとあの男の言葉が脳裏を過ぎった。
(『私が彼の女として利用価値を見出してあげよう』・・・って、どういうコト?)
これがあの男の言う利用価値だとしたら、何一つあの男に利益を齎して【もたらして】いない。
悪戯に彼を刺激して彼の士気を高めてしまっただけだ。
私にとっては彼の士気が上がることは良いことではある。そういう意味では利用価値はあったとも言える。
しかし、あの男が敵に塩を送るような真似をしないのはたった今、身を持って学習済みだ。
「・・・しかし、あれだけの出血だ。ヤツらは相当刺激されているだろうな。」
「ヤツら?・・・しまった!ネス!!」
(―――えっ?)
遠くで呟くようなあの男の声と殆ど同時に、私の目の前から地面を轟かす低い唸り声が聞こえだした。
そして姿を現したのはこの前窓の外に見つけた獣、サントドッグだった。
繁殖期を迎えたサントドッグは血の臭いを敏感に嗅ぎつけ、できる限り弱った獲物を狩ることで体力をつけようとする。
目の前のサントドッグは私の血の臭いに引き寄せられたのだ。
あの獣の世界では基本的に人間の女性は弱い動物と見られていて、しかも出血多量で満足に動けない今の私はあの獣にとって・・・。
(格好の、標的――!?)
「だぁぁーっ!・・・うぐっ!!」
「・・・えっ。」
私へ飛び掛ってきたサントドッグを彼が間に躍りこみ殴り飛ばした。
その次の瞬間、彼が呻き声を上げ硬直する。それから私の頭や背中にかかる温かい液体。
「う・・そ・・・し・・・ししょぉぉぉぉぉぉぉ!!」
私は残っていた力を振り絞って彼の名を叫んだ。
遠くであの男の嘲笑が聞こえ、そのまま何かを言い残して立ち去って行った。
後は放っておいても彼も私も死ぬと考えたのだろう。
実際、この時の私は漆黒の谷底に堕ちながらこのまま二人とも死んでしまうと思っていた。